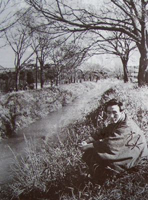[太宰の作品について]
筆者自身、太宰の全ての作品を読破している訳ではないのだが、よく言われる『青春文学』という枠で言い表すにはいささか勿体無い様な、とても奥深い、芸術論や文学論、また人生観等を盛り込んだ名作揃いだと思う。
自戒、自虐の念から精神的に追い詰められていた節もあり、入水自殺という残念な最期を遂げた為、作家性そのものをネガティブに捉えられる事もあるが、ユーモラスに描写した文章も多数発表しており、単純に娯楽作品としても楽しめる内容の物も多く、幅広い層に支持されるのも頷ける。
二人の作家が只ひたすら、お互いの思いをぶつける書簡を交わすだけという内容の『風の便り』や、人間主体ではなく猿の視点から描かれた『猿ヶ島』のように、ユニークな短編も数多く発表している。太宰作品として有名なのは、『人間失格』や『斜陽』、『パンドラの匣』等の長編小説だろうが、優れた短編やエッセイ等に目を向けると、太宰治という人間に親しみすらも感じられ、繰り返し何度読んでも飽きない面白さがある。
太宰作品に馴染みの無い人にはあまり知られていないだろうが、『如是我聞』という連載評論では、真っ向から文壇を相手に喧嘩を売る様な、挑発的で、恐らく太宰の本心をストレートに綴ったであろう内容となっており、非常に興味深い文章となっている。
また、処女短編集である『晩年』には、『人間失格』の原型とも取れる『道化の華』等も有り、数々の名作の雛形とでも言うべきか、昇華前の文章が楽しめる。
また、太宰は『斜陽』や『女生徒』、『きりぎりす』等、女性主人公の1人称視点で描かれた名作も多く発表しているが、男である太宰が何故ここまで女性の心理描写に長けているのか、甚だ不可思議ではある。(Wikipediaの情報にも、「特定の女性の日記が基になっている作品だからであるとの指摘がある」と書かれているが、それも確証がある訳ではない。)
[太宰と煙草]
太宰の作品を読んでいると、時折登場人物が煙草を吸う場面が出てくるのだが、その際殆どが『ゴールデンバット』を吸っている。
これは、太宰自身が『ゴールデンバット』を吸っていた為らしく、「タバコは両切りに限る。とくにバットに限る。」と語ったという逸話もあり、かくいう筆者自身も、太宰の影響から『バット』を吸うようになったクチである。
余談ではあるが、『ゴールデンバット』は日本で現在販売されている煙草の銘柄としては最古の超ロングセラー商品で、日本でタバコの専売制が開始されて間もない1906年(明治39年)9月に、当時の大蔵省専売局(後の日本専売公社の前身)から発売された。
太宰以外にも著名な作家に愛された銘柄であり、芥川龍之介や中原中也、博物学者の南方熊楠もこの煙草を吸っていたようである。
[太宰が生活した町]
太宰は青森県北津軽郡金木村(現・青森県五所川原市、旧北津軽郡金木町)で生まれ育ち、その後、東京帝国大学(現・東京大学)への進学を機に下宿暮らしを始め、左翼活動にのめり込んだ為に居所を転々とし、やがて戦災に遭い疎開しながらも、最終的には東京府北多摩郡三鷹村下連雀(現・東京都三鷹市)へと落ち着いた。
当時太宰が入水自殺をした玉川上水も、現在では小さく緩やかな流れのものになっているが、当時は水深も深く、流れも急だった為、自殺の名所としても有名だったようである。太宰の短編『乞食学生』には、以下のような文章もあり、曰く、「万助橋を過ぎ、もう、ここは井の頭公園の裏である。私は、なおも流れに沿うて、一心不乱に歩きつづける。この辺で、むかし松本訓導という優しい先生が、教え子を救おうとして、かえって自分が溺死なされた。川幅は、こんなに狭いが、ひどく深く、流れの力も強いという話である。この土地の人は、この川を、人喰い川と呼んで恐怖している。」とある。(この一節は太宰入水地の碑にも刻まれている。)
そして現在に至っても多くの太宰ファンが三鷹を訪れており、太宰の墓がある禅林寺では、遺体発見日である6月19日を桜桃忌として(命名は太宰と同郷であり、生前交流のあった作家、今 官一による。)、多くの人が彼の死を悼み弔いに訪れている。
また、(財)三鷹市芸術文化振興財団や、みたか都市観光協会では、『太宰プロジェクト』と題し、記念グッズの製作・販売等も行っているようだ。